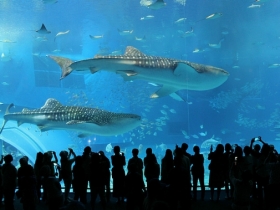絹糸の声
静かに宴は始まった。
空間に揺らぐゆったりとした三線(サンシン)の音色。
細い指がしなやかに三線の弦を行き来する。
グレーの品のある着物の首元には赤の襟がちらりと覗き、
彼女の「粋」さを際立たせている。
目を閉じたまま歌い出すその唄声は、
伸びやかでいて情感がある。
歌い出しの一瞬で
この場が彼女の世界に切り替わってしまう程の味ある深さだ。

大城美佐子の唄声は「絹糸の声」とも表現される程に
艶があって、柔らかい張りがある。
そこに三線の音色が絶妙に絡まっていく。
沖縄民謡を聴いていて感じることがある。
それはリズムが定まっているが
どこかで定まっていないという感覚だ。
淡々とリズムを刻むそれを実際に計ったら、
きっと一定なのかもしれない。
だけどそう感じさせない何かがある気がする。
そのリズムは唄の情感とぴったり寄り添い、
その時々で長くも短くも表現されるように聞こえる。
一音一音のあいだにある微妙な伸び、
その感覚は見えない部分としてある沖縄民謡の深みだと思う。


即興で遊ぶ
「沖縄の民謡は、唄というよりかは語り。
その時々で、いま何を唄うべきかをその時の感じで決める。」
と美佐子さんは言う。曲の歌詞は決まっているものでは…?
話を聞いてもよく分っていなかったその意味を、
ライブの後でお弟子さんの大城琢さんが教えてくれた。
「さっき唄ったうたは『豊節』『川平節』
そして『ナークニー』です。
『ナークニー』には、メロディーはあるけど
実は歌詞がしっかりとは定まっていない。
そこに、その時々で合うものを即興で選んでうたっていくんです。」
本土で言う「和歌」のように、
沖縄にも「琉歌」というものがある。
言葉だけでメロディーのないその琉歌を
「ナークニー」のメロディーにのせ、
男女で掛け合いながら即興でうたっているという。
それは誰にでも出来ることではない。
数多くある琉歌を理解し常に親しんでいないと、
直ぐに口からは出ないだろう。
豊富な経験も必要なので、
最近は難しいからとあまりやりたがらない人の方が多いらしい。
でも昔はこうやって掛け合いで唄遊びを楽しんでいた、
そんな技を沖縄では様々な所で見れたのだ。
ローカルの腕試し

民謡酒場は本来、地元の人達の腕試しの場であり、
歌や三線自慢のうちなーんちゅが集い
そこで演奏しては遊ぶような場所だったという。
「商業的ではない、これが本来のうたの楽しみ方です。」
そう言う琢さんは、
本当に沖縄民謡を愛しているんだなと思うほどに、
この日うたってくれた歌詞の意味をとても丁寧に教えてくれた。
そんな中、またライブが始まった。
今度は台湾からのお客さんが太鼓で飛び入り。
美佐子さんも三板(サンバ)を叩いて踊りだす。
ラストはお客さんも混ざってのカチャーシーで、
場は一気に盛り上がりを見せた。


沖縄民謡の奥深さは、それを生で体験することでしか味わえない。
「沖縄のポップスと民謡は違う。
若い人達も、いずれは本当の民謡に近づければ最高だね。」
カウンターに立つ美佐子さんは、そう言って微笑んだ。
文章 Hinata
写真 Yoshiaki Ida